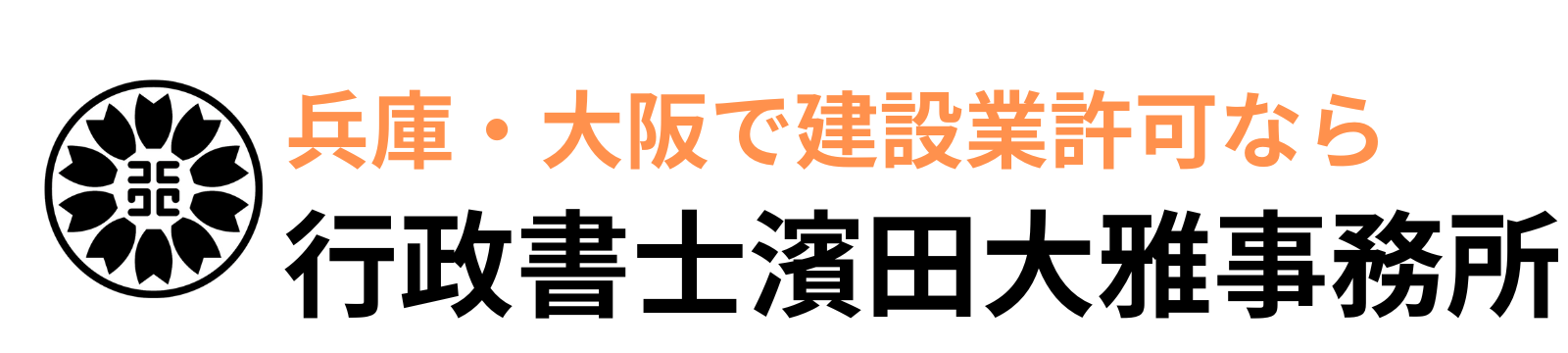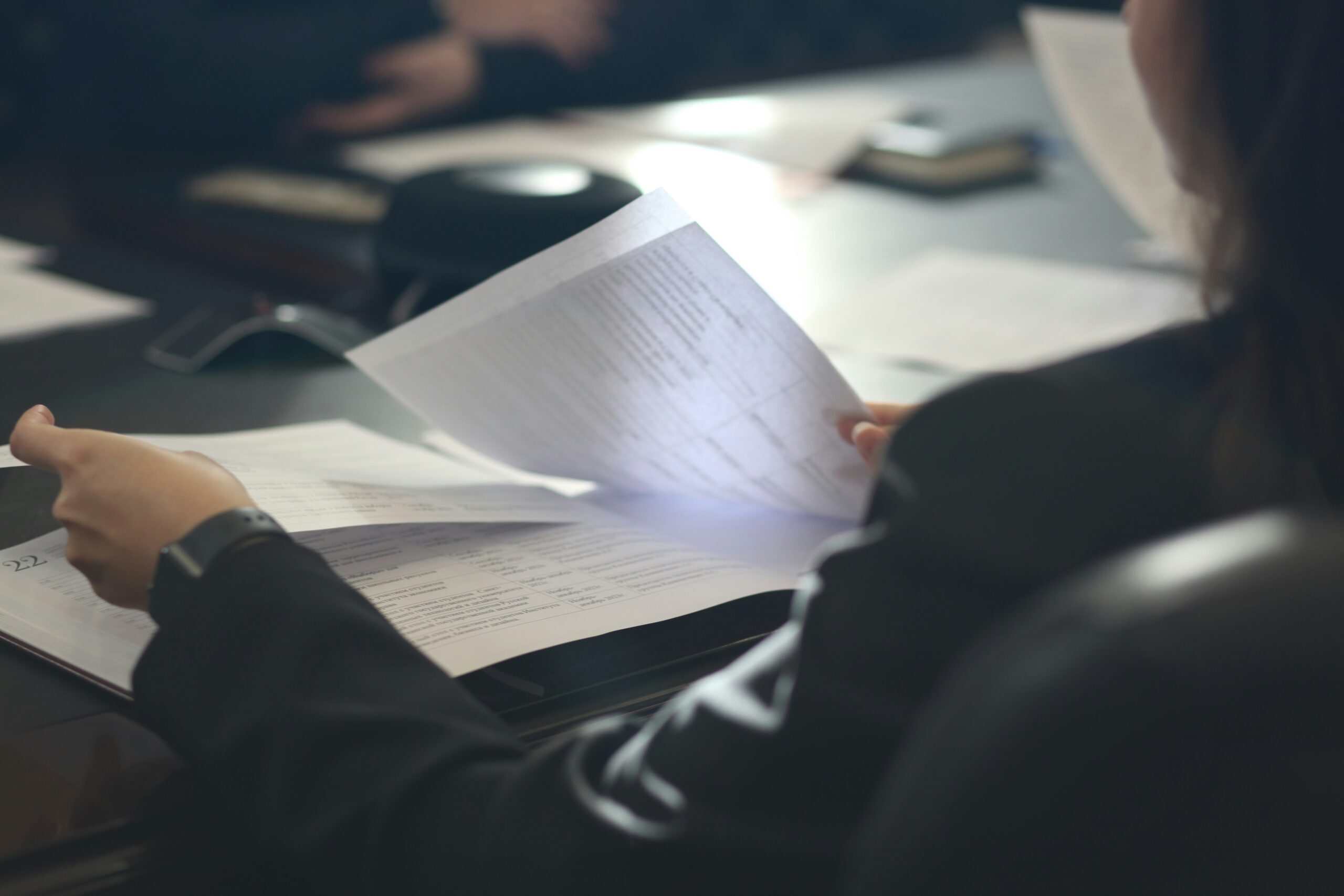建設業を営む上で必須となる「建設業許可」。この許可を取得するためには、技術力や財産的基盤といった様々な許可要件を満たすことに加え、「欠格要件」に該当しないことが極めて重要です。この欠格要件は、建設工事の請負契約を適切に履行できる誠実性や適格性を判断するための基準となります。
ここでは、建設業許可における欠格要件とは具体的にどのようなものか、そしてその要件に該当しないことを証明するために、法人と個人事業主それぞれにどのような書類が必要になるのかを詳しく解説していきます。
目次
- 建設業許可の「欠格要件」とは?
- 欠格要件の確認対象者
- 具体的な欠格要件の内容
- 欠格要件に該当しないことの証明書類
- まとめ
建設業許可の「欠格要件」とは?
建設業法は、建設業者の資質の向上や請負契約の適正化を目的としており、許可制度を通じて、事業者やその関係者が、建設業を営む上で不適格な状態にないかを確認します。
この「欠格要件」は、過去の行為や現在の状況において、建設業を営む上でふさわしくないとされる事由を定めています。
欠格要件の確認対象者
欠格要件の確認が必要となるのは、以下の者です。
個人の場合
- 個人事業主本人
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業部長など)
法人の場合
- 法人の役員等 (「役員等の一覧表(様式第1号別紙1)」に記載された者。顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、または出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者も含む)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者など)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業部長など)
【「建設業法施行令第3条に規定する使用人とは?】 「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結および履行において一定の権限を持つ者を指します。具体的には、支配人や、主たる営業所を除く支店または営業所の代表者がこれに該当します。これらの使用人は、原則として、その営業所における請負契約を総合的に管理し、休日を除き毎日所定の時間職務に従事していることが求められます。
【「役員等」とは?】 法人の場合、「役員等」には業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事など)が含まれます。また、取締役会の決議を経て、具体的な権限委譲を受けた執行役員等も該当します。さらに、役職名を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者として、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主や、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている個人も「役員等」として記載が必要です。
具体的な欠格要件の内容
以下のいずれかの事由に該当する場合、建設業許可を受けることはできません。
1.許可申請書または添付書類に虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けている場合。
2.成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ていない者。
◦ただし、医師の診断書により、契約の締結および履行に必要な認知、判断、意思疎通を適切に行う能力があると認められる場合は、欠格事由に該当しないとされます。
3.不正な手段で許可を受けた、または営業停止処分違反などで許可を取り消され、その取消しの日から5年が経過していない者。
4.許可取消し処分に係る行政手続法による通知(聴聞の通知)があった日から当該処分があった日までの間に、建設業を廃止した旨の届出をした者で、届出の日から5年が経過していない者。
5.上記の期間内(聴聞通知から処分決定まで)に廃業届出があった場合において、聴聞通知日前の60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人、または個人の政令で定める使用人であった者で、届出の日から5年が経過していない者。
6.営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
7.許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過していない者。
8.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
9.建設業法または一定の法令に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終え、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
◦一定の法令には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の一部(傷害、暴行、脅迫、背任など)、暴力行為等処罰に関する法律、建築基準法、労働基準法などが含まれます。
10.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者。
11.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当するもの。
12.法人で、役員等または政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者がいるもの(一部例外を除く)。
13.個人で、政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者がいるもの(一部例外を除く)。
14.暴力団員等がその事業活動を支配する者。
欠格要件に該当しないことの証明書類
欠格要件に該当しないことを示すためには、以下の書類を提出する必要があります。これらの書類は、発行後3か月以内のものが求められます。
1. 登記されていないことの証明書
目的: 成年被後見人および被保佐人に該当しないことを証明します。
記載事項: 氏名、生年月日、住所が記載されている必要があります。外国籍の方は国籍の記載があるものを提出します。
取得場所: 法務局で窓口申請が可能ですが、郵送申請は東京法務局のみで取り扱っています。
提出対象者
- 個人事業主本人
- 法人の役員(ただし、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、または出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者については提出不要です)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業部長など)
2. 身分証明書
目的: 本籍地の市区町村が発行し、以下の事項全てを証明するものです。
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。
- 後見の登記の通知を受けていないこと。
- 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと。
取得場所: 本籍地の市区町村が発行します。
提出対象者
- 個人事業主本人
- 法人の役員(ただし、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、または出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者については提出不要です)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業部長など)
外国籍の方: 身分証明書は発行されないため、「登記されていないことの証明書(国籍の記載があるもの)」のみの提出となります。
その他の留意事項
法定代理人について: 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が役員である場合、その法定代理人についても欠格要件の確認が必要となり、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)」および登記されていないことの証明書等が求められます。
医師の診断書について: 申請者や役員等が成年被後見人または被保佐人に該当する場合でも、医師の診断書を提出することで、建設業を適正に営むために必要な認知、判断、意思疎通を適切に行う能力があると認められれば、欠格要件に該当しないとされる場合があります。診断書には、具体的な診断名、所見、各種検査結果、判断能力(見当識、意思疎通、理解力・判断力、記憶力)の障害の有無とその程度などを詳細に記載する必要があります。
まとめ
建設業許可の取得は、事業の継続と発展に不可欠なステップです。そのためには、事業の規模や技術力だけでなく、「欠格要件に該当しない」という誠実性・適格性の証明が極めて重要となります。
法人として申請する場合も、個人事業主として申請する場合も、今回ご紹介した欠格要件と、それを証明するための書類を正確に理解し、漏れなく準備することが、スムーズな許可取得への第一歩となります。必要な書類を事前に確認し、確実に準備を進めましょう。ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。

行政書士濱田大雅事務所
濱田 大雅
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
| 事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
| 代表 | 濱田 大雅 |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
| TEL | 06−7777−6901 |
| メール | info@gyo-hamada.com |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |